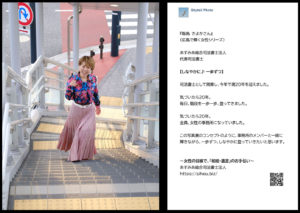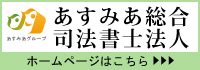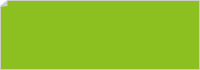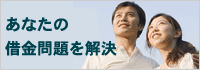司法書士の飯島です。
今日は、youtubeを撮影しました(^^♪
最近、「スタンドエフエム」っていうアプリにはまってて、よく聞いてるんです。
スマホで聞く、ラジオみたいな感じ。
いろんな方が、いろんなテーマで投稿してて、まさしくyoutubeのラジオ版って感じ。
この気楽な感じが、何かいいんです♪
そして、私もやってみたくなった(笑)
で、普段は、カメラを前にして話していたんですが、音声だけで収録してみました。
近日中にupしようと思います。
そこでのテーマが、
「いい士業事務所の見つけ方」♪
士業事務所というのは、「司法書士」とか「弁護士」とか「税理士」とか
いわゆる「●●士」っていう資格の事務所を言います。
この「●●士」に依頼することって、ビジネスされてる方は別として、
普通に生活していると、あんまり縁がない方がほとんどだと思います。
一生に一度とか。
私、士業事務所への依頼って、「結婚式場の依頼」とよく似てるな~って思ってます。
約15年前に、結婚式をあげた時に、式場と契約して、いろいろお願いしたのですが、
結婚式が終わった後に、
「これ聞いてみれば良かった」
とか
「こうすれば良かった」とか、いろいろ出てきました。
でも、もう、やり直すことが無いというか、その時の経験って、その後、活かす機会って、ないんですよね~。
当時、この経験、他で活かしたいって、すごく思ってました。
うちの事務所は、「相続」手続きをお手伝いすることが多いのですが、
「相続」って、人生で何度も経験することってないですよね。
だから、いざ「依頼しよう」って思った時に、
どこに依頼したらいいの?
って、迷うことも多いと思います。
多くの方が、インターネットで検索して、事務所を探すと思いますので、
ネットで検索する時に、「基準にしてほしいことを3つ」というテーマでお話ししました。
1つ目は
「料金基準がキチンと提示されているかどうか」
なぜか、
それは、
「料金を提示できるということは、その分野にある程度、経験があって、
きちんと事務所経営できている」指標になるからです。
この「料金」って、提供する側からすると、すごく難しいんです。
「同じ相続」でも、ケースによって必要な手続きが変わってくるので、
最初から、料金を提示するのって、まぁ、難しい。
だから、最終的な金額は、見積もりさせていただく流れになるんですが、
料金の基準は、キチンと示してある事務所がいいと思います。
因みに、司法書士って、昔、料金が、司法書士会で決まってたんです。
全国、どこの事務所に依頼しても、料金は一律。
私が開業した時に、書士会から、いろんな資料をもらったんですが、その時に、「料金表」ももらいました。
立派な厚紙で、かなり大きな料金表で、これを事務所に掲示しなければなりませんでした。
それが、報酬が撤廃されて、各事務所が自由に決めれるようになりました。
報酬が撤廃されると同時に、事務所ごとで、いろんなサービス提供できるようになったので、
例えば、相続でも、「相続丸ごとパック」みたいなサービスで、料金を設定したりできるようになりました。
つまり、その事務所が、どのような料金体系を提示しているかで、どれだけ、その事務所に経験があるかとか、
キチンとしてるかが、分かるようになったと言えると思います。
弁護士さんのサイトとかで多いのが、「成功報酬の〇〇%」。
この成功報酬をどのようにカウントするのか、文章で説明してあっても、すぐに理解するのは難しいです。
一律、料金を明確にできないものもあるから、「金額が定まっている」必要は無くて、
基準が明示されてるかどうかを、判断基準にしてもらったらいいと思います。
2つ目は
「顔が見えるかどうか」
顔って、必ずしも、写真が必要というわけではないと思っています。
サイトって、その事務所の考え方というか、事務所運営の指標が、分かりやすく表れてると思っています。
例えば、「高層ビル」をバックに、「ビジネスに強い」という雰囲気の事務所もあれば、「手作りで作ってます」みたいなサイトもある。
どっちがいいとかは、全くないです。
「顔」というのは、事務所の考え方という意味で、どんなサイトを作っているかで、事務所がどんな考え方をしてるかは、ある程度、判断できると思います。
だから、自分は、どんな事務所に相談したいのか、っていう事を、明確にした上で、各事務所のサイトを見てもらうと、
自分に合った事務所を見つけやすいと思います。
3つ目
「実際にコンタクトを取ってみる」
電話で問い合わせるでもいいし、実際に相談に行って見るという方法でもいいと思います。
電話の対応で、ある程度、分かったりしますよね。
その時には、「この人にお願いしよう」って、自分が思えるかどうかが、とっても大事です。
せっかく相談に行っても、
何か怖くて、自分が質問したいことが聞けない。
とか、
自分がやったことを否定されて怒られたとか。
当たり前ですが、相談者の方と士業事務所の人間の間には、圧倒的な知識の差があります。
だから、知識を合わせようとする必要はないと思います。
それより、自分が疑問に思ったこととか、自分がお願いしたいと思ってことを、素直に伝えられるかどうか。
ここを判断基準にしてほしいです。
その相談に対して、士業は、できる方法を考えますし、「できない事は、できない」って伝えます。
士業って、資格を取るために、頑張って勉強した人たちで、その知識を使って、問題を解決するお手伝いをしたい
って思っている人がほとんどだと思います。
正直、割に合わないことも多いし、お金儲けだけ考えるのなら、他に割りのいいビジネスはあると思います。
だから、「お金儲けできれば、何でもいい!!」っていう考えの人は、士業って向いてないです。
相談する方は、とにかく、
自分がどうなったらいいか、っていうのを相談してもらって、方法は士業に任せる。
そういうスタンスがいいと思っています。
そのためには、自分の意見をきちんと伝えられる人かどうか、
っていうのを、判断基準にしてもらえたら、間違いないかなと思います。